芸術はつねに幻想への距離に依存する
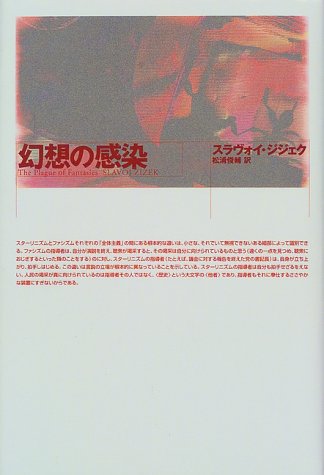 幻想が有効に機能するためには、それはあくまで「暗黙」でなければならず、それによって支えられる、明示的な象徴の生地に対する距離を維持し、その内在的な逸脱として機能しなければならない。明示的な象徴の生地とその幻想の背景との間の根幹を成す溝は、どんな芸術作品にも明らかである。場所の方がそこを埋める要素よりも優先されるため、芸術作品はいくら調和的でも、そもそも断片的であり、その場所に対して不足している。芸術が成功する「仕掛け」は、芸術家がもつ、その不利を利点に転じる能力にある──中心的な空虚とそれを囲む諸要素におけるその共鳴をうまく操作するのである。そうすると、「ミロのヴィーナスの逆説」も説明できる。今日においては、この像の腕が欠けているのはもう欠陥とは感じられておらず、逆に、その美的衝撃力の具体的な構成要素と感じられている。頭の中で簡単な実験をすれば、この判断が確かめられる。損傷のない、完全な像を想像すれば(一九世紀には、美術史家は、実際にせっせとそれを「補完」しようとしていた。いろいろな「再現像」があり、その手には槍や、松明や、鏡まであった・・・)、結果は紛れもなく
幻想が有効に機能するためには、それはあくまで「暗黙」でなければならず、それによって支えられる、明示的な象徴の生地に対する距離を維持し、その内在的な逸脱として機能しなければならない。明示的な象徴の生地とその幻想の背景との間の根幹を成す溝は、どんな芸術作品にも明らかである。場所の方がそこを埋める要素よりも優先されるため、芸術作品はいくら調和的でも、そもそも断片的であり、その場所に対して不足している。芸術が成功する「仕掛け」は、芸術家がもつ、その不利を利点に転じる能力にある──中心的な空虚とそれを囲む諸要素におけるその共鳴をうまく操作するのである。そうすると、「ミロのヴィーナスの逆説」も説明できる。今日においては、この像の腕が欠けているのはもう欠陥とは感じられておらず、逆に、その美的衝撃力の具体的な構成要素と感じられている。頭の中で簡単な実験をすれば、この判断が確かめられる。損傷のない、完全な像を想像すれば(一九世紀には、美術史家は、実際にせっせとそれを「補完」しようとしていた。いろいろな「再現像」があり、その手には槍や、松明や、鏡まであった・・・)、結果は紛れもなく
芸術はこのように断片的なものである。それがいくらか有機的<全体>であってもそうである。芸術はつねに幻想への距離に依存するものなのだ。イーディス・ウォーストンは、その未完の物語「ベアトリーチェ・パルマート」の「未発表の断片」において、父と娘が、相互の性器を愛撫しあい、クリニングスとフェラチオをし、もちろん本番もするという近親相姦の様子を、詳細に、成人映画なみに記述している。手早く精神分析的説明をしてみせるのは簡単なことである。この断片は、「<母>の<ノー>」(ウォートンについてのエーリクの本の章のタイトル)というシンタグマに最もよく集約される、ウォートンの文学作品全体に対する「鍵」をもたらすというものである。ウォートンの核にある家族にあっては、禁止の実行行為者としてふるまうのは母であり、父は一種の禁じられた知識、享楽がしみ込んだ存在を体現している。さらに、ここで幼児の性的虐待のゲームを演じ、十分な「状況証拠」から、ウォートンは父親に性的な虐待を受けていてそれがトラウマをもたらす出来事となって、彼女の人生や文学的歩みの特徴となったことを示唆すると指摘するのもたやすい。幻想と「現実」の間の両義性を強調し、両者のそれぞれの部分を明瞭に区別するのは難しいと言うことも簡単だ(父の近親相姦は彼女の幻想にすぎないのか、それともこの幻想は「現実の」性的虐待によって引き起こされているのか)。いずれにせよ、この悪循環は、イーティスは「無垢」ではないという事実を証言している。彼女は幻想のレベルで近親相姦に荷担しているのだ。しかしこうしたアプローチでは、芸術家が幻想から除去する場合の方が、それを直接提示する場合よりも真実があるということを認識できない。よくあるメロドラマやキッチュは、「真の芸術」よりも幻想の方にずっと近い。言い換えれば、「元の幻想」の歪みを説明するためには、社会的な禁止に言及するだけでは十分ではなく、禁止の姿をして介入するのは、幻想そのものが「原初の嘘」、根本的な不可能性を隠す
スラヴォイ・ジジェク『幻想の感染』青土社 1999年
TrackBack URL :
Comments (0)